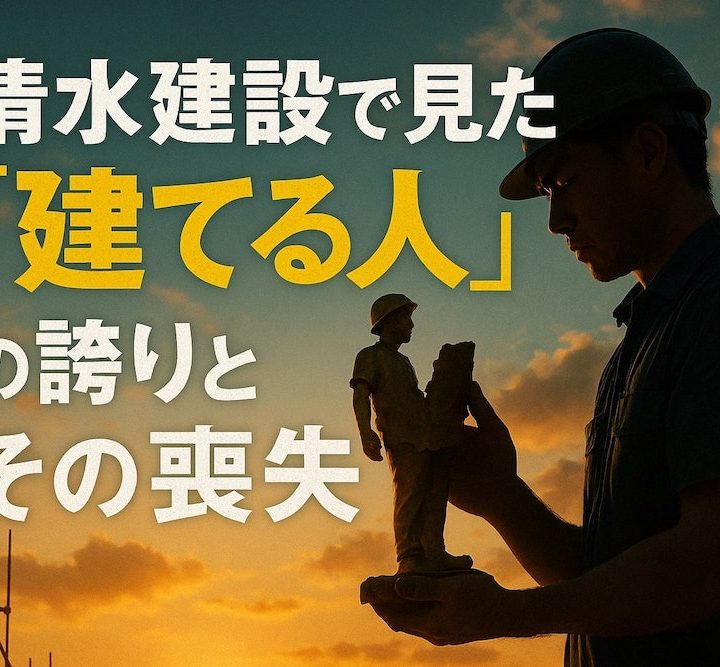高層ビルの骨組みが空へと伸びていく姿を、誰もが一度は目にしたことがあるだろう。
その鉄骨の上で、地上80メートルの風に吹かれながら黙々と働く人々の姿がある。
彼らは「建てる人」と呼ばれる、現代の縁の下の力持ちだ。
私が清水建設に入社した1990年、バブル経済の終焉を目前に建設ラッシュは最後の輝きを放っていた。
それから18年間、私は現場監督として数多くの建物の誕生に立ち会ってきた。
そこで目にしたのは、誇り高き「建てる人」たちの姿と、やがて訪れるその誇りの静かな喪失だった。
本稿では、元・現場監督の視点から、建設業界で起きている「人」のドラマを紐解いていきたい。
「建てる人」の誇りとは何か
現場に宿るプロフェッショナリズム
「この鉄骨、3ミリずれとるぞ」
冬の朝、マイナス2度の現場で聞こえてきた鉄骨職人の声は、今でも耳に残っている。
図面通りの精度を追求する姿勢は、どんな悪条件でも揺るがなかった。
現場に立つ職人たちは、自分の仕事に対して妥協を許さない厳しさを持っていた。
それは単なる几帳面さではなく、「自分の仕事が建物の安全を支える」という重大な責任感から生まれるプロフェッショナリズムだった。
彼らにとって建物は、単なる構造物ではなく、自分の魂の一部が宿る作品だったのである。
清水建設での日々に見た職人たちの魂
清水建設の現場で最も印象に残っているのは、一人ひとりの職人が持つ「技術への誇り」だった。
鉄筋工は結束線を結ぶ音だけで適切な強度かどうかを判断し、塗装工は塗料の粘度を指先の感覚だけで調整する。
そんな技を持つ職人たちが現場に集まり、一つの建物を作り上げていく。
「俺の仕事が見えなくなるのは、次の工程がきちんとできている証拠だ」
内装工事の職人がそう語ったことがある。
自分の仕事が壁の中に隠れることを誇りに思う―それは他者の目に触れなくても、自分の技術に最高のクオリティを求める矜持の表れだった。
技術と心意気が支えた”ものづくり”の現場
建設現場では、「技術」と「心意気」が不可分のものとして存在していた。
技術は継承されるものであり、心意気は伝承されるものだった。
雨の日も風の日も、朝一番に現場に到着する土工の棟梁。
彼の姿を見て、若い職人たちは言葉以上のものを学んでいた。
「この仕事は自分の子や孫の代まで残る。手抜きなんてできるか」
そんな言葉を、現場で何度聞いたことだろう。
建設業における「ものづくり」とは、単に物理的な構造物を作ることではなく、次の世代へと続く文化を作ることでもあった。
誇りが揺らぎ始めたとき
バブル崩壊後の現場と働く人々の変化
1990年代初頭、バブル経済が崩壊すると、建設業界は大きな転換点を迎えた。
それまでの「より高く、より大きく」という価値観から、「いかにコストを抑えるか」という価値観への変化だ。
清水建設でも、コスト削減の波は容赦なく現場へと押し寄せた。
「工期を2週間短縮」「人員を15%削減」―そんな指示が本社から次々と届くようになった。
職人たちの表情に、少しずつ暗い影が落ち始めるのを感じた。
建設業就業者数は、1997年の685万人をピークに減少が続き、2023年には483万人まで減少した。
この数字の背景には、多くの職人たちの離職があったのだ。
若手技術者の離職が示すもの
「もう、この仕事続けられません」
入社3年目の若手技術者からそう告げられたのは、2003年のことだった。
彼は優秀な技術者だったが、休日出勤の連続と終わらない残業に心身ともに疲弊していた。
建設業では人手不足が深刻化し、一人あたりの業務負担が大きくなり、長期間労働が当たり前になっている。
若手の離職率が高まる中、私が目にしたのは「誇り」だけでは若者を繋ぎとめられない現実だった。
建設業の新規学卒入職者は2022年に4万3000人で、10年前から5000人増加しているにもかかわらず、人手不足が続いている。
この矛盾は何を意味するのか。
それは若者が入ってきても定着しないという深刻な問題を示していた。
“誇り”と”待遇”の乖離
「誇りだけでは家族を養えない」
現場で30年以上働いてきたベテラン職人の言葉が、胸に刺さった。
バブル崩壊後、建設業界では価格競争が激化し、それが職人の賃金にも影響を与えていた。
建設業界の賃金が上昇傾向にあるとはいえ、生産労働者の給与は依然として製造業よりも低い状況が続いている。
誇りと待遇の乖離は、年々広がっていくように感じられた。
雨風をしのげない現場で、危険と隣り合わせの仕事をしながら、その対価が適正といえるのか。
働く人々の目に宿る誇りの光が、少しずつ弱まっていくのを見るのは、現場監督として最も辛い経験だった。
技術継承の難しさと組織の歪み
現場で起きていた技能の断絶
清水建設の現場で、私が最も危機感を覚えたのは技能の断絶だった。
「昔は5年かけて教えていたことを、今は1年で覚えろと言われる」
ベテランの左官職人がそう嘆くのを聞いたとき、技術継承の危うさを痛感した。
建設現場では、本来、経験と時間をかけて技術を磨き、それを若手に伝えていくという文化があった。
しかし、工期短縮とコスト削減の圧力の中で、そのサイクルが崩れていった。
職人技は一朝一夕に身につくものではない。
だが、その当たり前のことが、効率化という名の下に軽視されるようになっていた。
教える文化の喪失と「教えられない若手」問題
「教える側も教わる側も、時間がない」
これは、多くの現場で耳にした嘆きだった。
かつては親方が弟子に技を伝える時間的余裕があり、弟子も一つの技を何度も失敗しながら身につける環境があった。
しかし、工期が厳しくなるにつれ、そうした時間的余裕は失われていった。
建設業界では、デジタル化による業務効率化が進められているが、それだけでは技能伝承の問題は解決できない。
また、「教えられない若手」という問題も浮上してきた。
これは若者の能力の問題ではなく、教わる姿勢や基礎的な体力、忍耐力の変化を指している。
両者の間にある溝は、単なる世代間ギャップではなく、社会構造の変化が生み出した深い亀裂だった。
現場から離れて見えた組織の限界
2008年、私が清水建設を去る決断をしたとき、組織の限界を感じていた。
大手ゼネコンという組織は、効率性と収益性を追求する中で、「人」を育てる視点を次第に失っていったように思える。
「人材」ではなく「人財」という言葉がよく使われるようになったが、実態は逆に人をコストとして見る風潮が強まっていた。
建設業界は、ICTと建設業の知見をかけ合わせることで課題解決を目指しているが、テクノロジーだけでは解決できない問題がある。
それは、人と人とのつながりの中で育まれる「信頼」や「誇り」といった目に見えない価値だ。
組織は数字で測れるものを重視するあまり、測れないものの大切さを見失っていたのではないだろうか。
「伝える」という第二の使命
コラム執筆から始まった”伝える仕事”
清水建設の社内報に寄稿したコラムがきっかけだった。
「佐伯さんの文章、現場の若手に響いたよ」
先輩からそう言われた時、私は自分の中に眠っていた「伝える力」に気づいた。
現場監督としての経験を言葉にすることで、直接指導できない多くの若手にも何かを残せるのではないか。
そんな思いから、社内報のコラムを定期的に書くようになった。
「コンクリートの養生と人材育成は似ている」
「安全確認の習慣は、信頼関係の第一歩」
現場で感じたことを、自分なりの言葉で紡いでいくうちに、もっと広く「建てる人」の姿を伝えたいという思いが強くなっていった。
言葉で守る現場とは何か
「言葉は、消えゆく技術を記録する最後の砦になる」
そう考えるようになったのは、ある職人の言葉がきっかけだった。
「俺の技は俺が死んだら消える。せめて、どんな思いでこの仕事をしてきたか、誰かに知ってほしい」
その職人は、特殊な左官技術を持っていたが、後継者がいなかった。
建設業界は小規模企業が多く、技術の継承が困難になっている。
言葉で記録することは、技術そのものを伝えることはできないが、その背景にある思いや哲学は伝えられる。
そして、その思いが誰かの心に火をつけ、新たな技術へと発展する可能性を秘めている。
言葉で守る現場とは、職人の魂を後世に伝えることだと気づいたのだ。
フリーライターとしての再出発と気づき
50歳を前に、私は清水建設を退職し、フリーライターとして再出発した。
「なぜ、安定した会社を辞めるのか」と問われることも多かったが、私の中では明確な使命感があった。
現場監督として見てきた「建てる人」の誇りと苦悩を、社会に伝えることが自分の役割だと感じていた。
フリーになって気づいたのは、建設業界の外から見ると、現場の実態がほとんど伝わっていないという現実だった。
建設業と言えば現場職のイメージが強いが、実は正社員の2割前後が事務職であり、アナログ業務が多い。
このギャップを埋めることこそ、私がライターとして取り組むべき課題だと確信した。
現場の「リアル」を伝えることで、建設業界と社会の間の橋渡しになりたいと思ったのだ。
働き続けられる現場を目指して
「誇り」を取り戻すための環境改革
建設現場に「誇り」を取り戻すには、環境改革が不可欠だ。
それは単に労働時間を短縮するといった表面的な対策ではなく、働く人が「価値ある仕事をしている」と実感できる環境づくりを意味する。
建設業界は2024年4月から時間外労働に上限規制が適用され、長時間労働の是正が求められている。
この「2024年問題」は危機ではあるが、業界変革のチャンスでもある。
「制約があるからこそ、新しい働き方が生まれる」
これは私が現場監督時代に大切にしていた言葉だ。
安全対策や品質管理など、現場では「制約」が「創意工夫」を生み出してきた。
同様に、労働時間の制約は、より効率的で人間らしい働き方を模索するきっかけになるはずだ。
実際に、BRANUが提供する建設業界向けDXソリューションのような取り組みが、業界の課題解決に貢献している例も増えてきている。
デジタル技術を活用して施工管理や採用、経営管理などを効率化することで、「人」に焦点を当てた環境づくりが可能になってきているのだ。
人が育ち、根づく職場の条件
私が清水建設での経験から学んだ、人が育ち根づく職場の条件は以下の3つだ。
1. 技術的挑戦の機会
- 難易度の高い仕事に挑戦できる環境
- 失敗から学ぶことを許容する文化
- 技術向上を評価する仕組み
2. 心理的安全性の確保
- 質問や意見を自由に言える風土
- 立場に関わらず尊重される関係性
- 多様な働き方を認める柔軟性
3. 未来への展望
- キャリアパスの明確化
- 社会的意義の実感
- 技術と経験の適正な評価
「2024年問題」をチャンスととらえ、最新機器の投入、業務のデジタル化、月給制への移行や人事評価制度の導入など労働環境整備に成功している会社も多い。
これらの条件が満たされることで、若者が「この業界で働き続けたい」と思える環境が生まれるのではないだろうか。
現場に必要なのは”人を見つめる視線”
建設現場の本質は、技術や設備ではなく「人」にある。
どんなに優れた建設機械や設計ソフトがあっても、それを使うのは人間だ。
その人間をどう見つめるかが、現場の質を決める。
私が現場監督として心がけていたのは、一人ひとりの表情を見ることだった。
「今日のあの職人は、いつもと様子が違う」
「若手が無理をして危険な作業をしていないか」
そうした些細な変化に気づける”人を見つめる視線”が、事故を防ぎ、良い仕事を生み出す土壌となる。
建設業界では中長期的な育成やリスキリング(学び直し)を前提に、未経験者の採用を行う企業が増え始めている。
このような新しい流れは、「人」に焦点を当てた変革の兆しとも言えるだろう。
目先の生産性だけではなく、働く人の成長と幸福を見据えた視点が、これからの建設業には不可欠なのだ。
まとめ
私が清水建設で18年間、現場監督として見てきた「建てる人」の姿は、誇りと技術への愛情に満ちていた。
しかし、バブル崩壊後の経済環境の変化は、その誇りを少しずつ浸食していった。
「建てること」は単なる経済活動ではない。
それは人間の営みの中でも最も根源的な文化であり、社会の基盤を支える重要な活動だ。
現場経験から紡ぎ出される「建設業の物語」は、技術書には書かれていない知恵と哲学を伝える役割を持つ。
建設業が直面する課題は、単に労働条件や技術革新だけでは解決できない。
必要なのは、「建てる人」を社会全体で支える意識と仕組みだ。
人材不足を解決する対策としては、労働者の処遇改善や、長時間労働をなくす働き方改革の推進、作業の効率化などが挙げられる。
次世代へのメッセージとして伝えたいのは、建設業の本質は「ものづくり」の誇りにあるということ。
その誇りを守り、育て、次代に伝えていくことが、私たちの責任ではないだろうか。
建物は時を経て老朽化するかもしれないが、「建てる人」の魂は、言葉となって永く受け継がれていく。
それが私の願いであり、フリーライターとして筆を取る原動力なのだ。
最終更新日 2025年8月6日